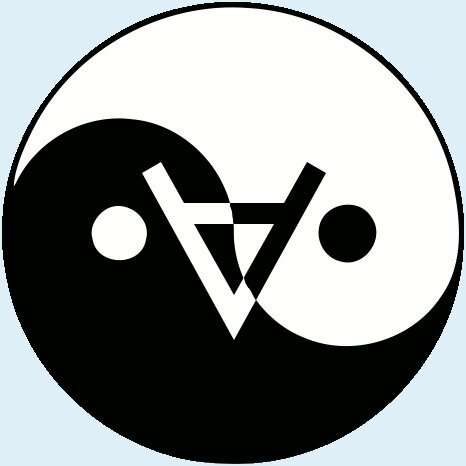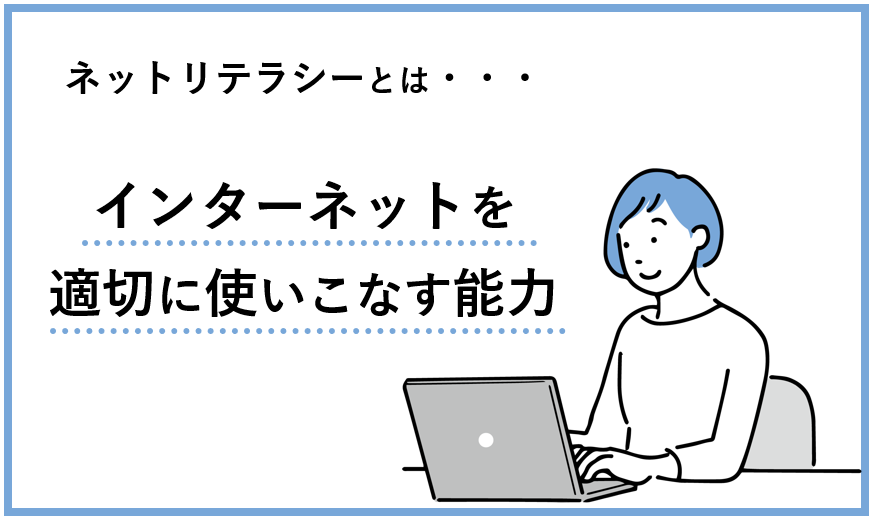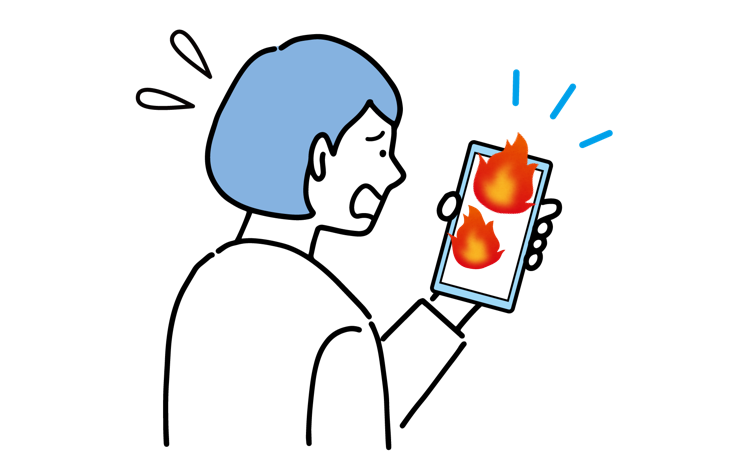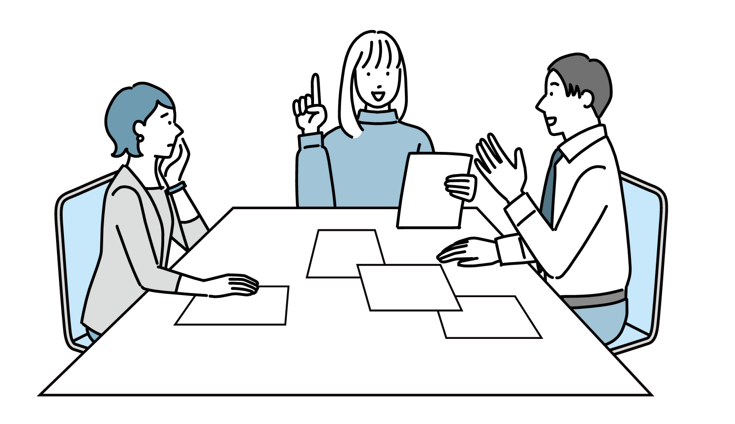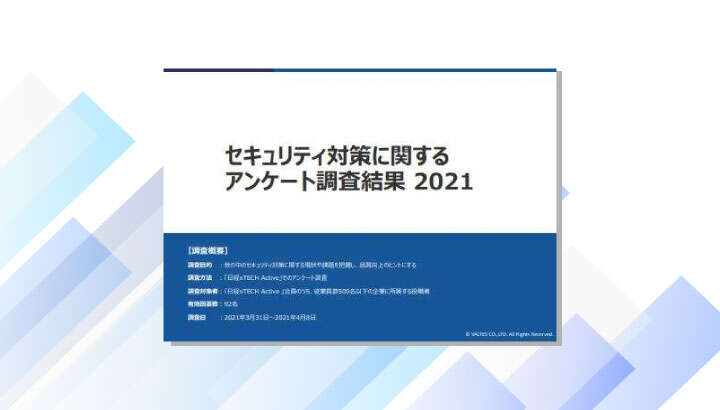誰もがスマートフォンを持ち、Twitterやインスタグラム、TikTokなどソーシャルメディアで企業や個人は、手軽に情報発信できるようになりました。
その反面、不用意な発信を行った結果、批判が殺到する「炎上」などの案件も数多く発生しています。
企業にとって「信用」は第一。毀損されることはブランドや事業の存続にすら影響を与えかねないものであり、炎上は決して起こしてはならないことです。
同様に、パソコンやUSBメモリなど持ち運べるIT機器の高性能化・大容量化により、大量かつ貴重な情報の紛失や漏洩が起こりやすくなっています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる現代、情報資産およびIT資産は企業の生命線であり、紛失や漏洩はなんとしてでも防がねばなりません。
炎上や情報漏洩といった事態を回避するために、個人個人が認識しておく必要があるのが、「ネットリテラシー」です。
今回は企業にとってのネットリテラシーに関する情報をまとめてみました。
- もくじ[非表示]
1.「ネットリテラシー」とは?
ネットリテラシーとは「インターネットを適切に使いこなす能力」のことを言います。
リテラシーの元となる英単語「literacy」は「識字能力(読み書きできる)」という意味で、ビジネスにおいては「情報を適切に理解、解釈して活用すること」という意味合いで用いられています。
単に「ネットリテラシー」といっても、その対象は広く、企業の情報発信管理や未成年の子供たちが安全にネットを使えるように心がけることなども含まれます。
これらを踏まえ、本記事では企業および所属する個人にとってのネットリテラシーについて解説していきます。
2.個人の炎上で企業に大きな損害を与えることも
今やネット、特にソーシャルメディアにおいて「炎上」の文字を見ない日はないと言えるほど、炎上は日常化しています。
そして、個人の炎上によって、企業に大きなダメージを与えることもあります。
例えば、かつてコンビニエンスストアのアルバイト店員が冷凍食品の陳列用ショーケースに入ってみせた写真をSNSに公開したことで大問題となりました。
「バイトテロ」とも呼ばれるこのような悪ふざけからの炎上は、該当店舗が閉店に追い込まれる結果となりました。
また、銀行や小売店などに著名人が来店した際に、店員が彼らを撮影した写真や購入した品物をSNSに公開して炎上したケースもあります。
著名人相手とはいえこれは重大なプライバシーの侵害であり、到底許されるものではありません。
他にも、企業アカウントの担当者が企業広報用アカウントと自身のプライベートアカウントを取り違えて投稿し、企業アカウントで誹謗中傷や品のないツイートをしてしまうような事例もありました。
一度ネットで広まってしまった情報は完全に消し去ることができないという問題も大きいです。
ネットにおける汚名(stigma、スティグマ)、あるいはネット上に半永久的に残る痕跡から「デジタル・タトゥー」とも呼ばれ、投稿者本人の意思とは無関係に非常に長く残り、時に拡散していきます。
3.企業が策定すべき2つのガイドライン
炎上が起きてしまう最大の原因は、やはりユーザーの不用意・非常識な情報発信「=ネットリテラシーの不足」だと考えられます。
では企業や団体は、どうすれば組織としてネットリテラシーを備えることができるのでしょうか?
中には、「SNSを使うからトラブルが起きる。だからうちはSNSやらない!」と極端な対応をするところもあります。
しかしSNSが社会インフラ化しつつある現在、組織としてSNSをやらないという選択は決して良い判断ではありません。なぜなら、SNSをメインに使っているユーザーから見たら、その企業や団体は存在しないことと同じ意味になるからです。
そのような状況を避けつつ、さらにネットの危険な点を正しく認識しネットやSNSに強い企業となるためには、企業としてのルールを決めておくことが大切です。
この章では、企業が策定すべき2つのガイドラインについて解説していきます。
SNS利用時の指針「ソーシャルメディアガイドライン」
ソーシャルメディアガイドラインとは、広義では「インターネットを利用するすべての利用者が守るべき指針や決まりごと」です。
2010年代からソーシャルメディアガイドラインを作成する企業や団体が増え、今では多くの企業・団体が、自らのネットへの関わり方に関する指針として作成しています。
例として、日清製粉グループをご紹介します。
日清製粉では「法律と社内のルールに従うこと」「ソーシャルメディアの性質を理解して発信すること」が明記されています。
ネットを利用する際に当然のことのように思えますが、これらが利用者の一部に正しく理解されていなかったからこそ炎上案件が起き続けているわけです。
このガイドラインは、ネットを利用する際のエッセンスが凝縮されたものと言えるでしょう。
もうひとつの例として、ガイドラインの例として、日本赤十字社のソーシャルメディアガイドラインを紹介します。
PDF5ページ分に及ぶ詳細な内容です。
特に私的利用の際にも遵守すべき項目として「就業時間中には利用しないこと」を挙げるなど、具体的に守るべき事項が記されています。
情報の取扱い指針「情報セキュリティポリシー」
情報セキュリティポリシーは企業・団体が定めるもので、「自らが保持する情報の取り扱いに関する方針をまとめたもの」です。
企業活動とITが切っても切れない関係となった昨今、情報セキュリティポリシーはすべての企業が策定すべきものといっても過言ではありません。
このようなポリシーの必要性は理解していても、策定担当者が決めるべきルールの具体的なイメージをつかむのが難しい場合には、総務省が公開しているページが参考になります。
ここでは、攻撃に対する予防だけでなく破られた場合の対処が必要であることや、一度作ったら終わりではなく見直しが必要であることなど、具体的なポイントが紹介されています。
4. 炎上を防ぐには、なによりも「教育」が重要
2章でご紹介したような炎上を防ぐためには、ガイドラインの策定だけでなく社員に対して「教育」を行うことも重要です。
中には、「言われなくてもわかっている」という態度をとる方もいるかもしれませんが、セキュリティ関連は進化が速く、かつての常識が通用しないこともよくあります。
すべての関係者が、他人事ではなく「自分事」として、これらの方針について学べるようにすることが大切です。
また、業種によっては、勤務内容に関わることについての私的なSNSの使用、情報発信についても、明確なルールを設ける必要があります。
特に雇用期間が比較的短いアルバイトを雇用する場合、時間と手間はかかってもネットリテラシー教育を実施することが大切です。
これはバイトテロを防ぐために必要なコストだと言って良いでしょう。
まとめ
「ネットリテラシー」とは、「インターネットを適切に使いこなす能力」のことです。
企業にとって望ましくない事態を避けるためには、ネットリテラシーの向上が不可欠です。
そのためにも、以下のような対策を行っていきましょう。
- 社内でルール・ガイドラインを策定し関係者全員へ周知する
- 関係者へネットリテラシーに関する教育を行う
個人の炎上によって企業は多大な損害を受けることも十分考えられます。あらかじめ炎上による被害を防ぐ対策をとっておくことが重要です。



 2023.04.14
2023.04.14